WebORCAとは?おもな特徴や利用手順・申し込み方法を解説
WebORCAとは?おもな特徴や利用手順・申し込み方法を解説
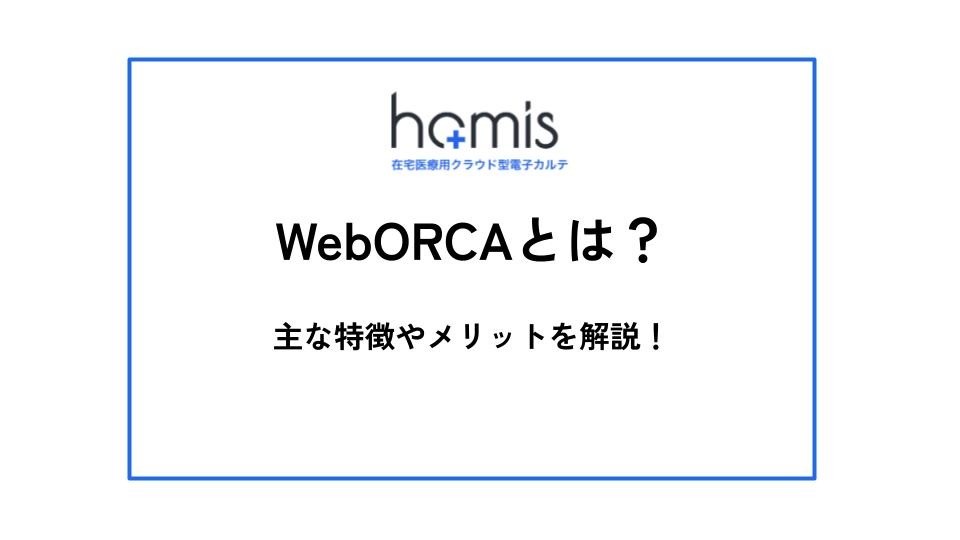
「WebORCAの機能や利点がわからない」
これから新しいクラウドシステムの導入を検討している医師のなかには、このように疑問を感じている方がいるのではないでしょうか。
本記事では、WebORCAと旧クラウド版の違いやおもな特徴、利用手順やお申し込み方法について解説します。
WebORCAの利点を知り、今後の導入に関する検討材料としてください。
WebORCAとは?
ORCAは、医療現場のIT化を推進するために作られたソフトウェアです。レセコンのなかでも導入率が高く、約17,000以上の医療機関で利用されています。
医療現場に導入されているORCAは、誰でも閲覧・更新できる仕組みになっており、常に細心の状態に維持されているのが特徴です。
WebORCAでは、患者さんの保険情報や個人情報が漏洩されないよう、ガイドラインに準拠した設計となっています。
WebORCAと旧クラウド版との違い
WebORCAと旧クラウド版とのおもな違いは以下のとおり。
- 動作速度
- ブラウザ利用の可否
- アクセス制限
- 災害に対する安定性
- サービスの価格体系
- オンプレミス(院内型)運用の可否
WebORCAでは、システムの動作が大幅に向上し、ブラウザで利用できるようになりました。
また、アクセス数が増大し、突発的な災害に対しても対応ができるようになっています。サービスの価格体系もシンプルになっているのが特徴です。
院内にサーバーを設置するオンプレミス(院内型)としても利用できる点もメリットといえます。
WebORCAの特徴
WebORCAは医療機関に必要な機能を備えたクラウドシステムです。おもな特徴は以下のとおりです。
あらゆるシーンで利用できる
WebORCAを運用する場合、インターネットに接続できる端末があれば、さまざまなOS・ハードウェア環境で利用できます。
在宅医療にて、訪問先でも利用できるため、その場で処方せんや請求書を発行したり、訪問先でレセプトの確認をしたりできます。
多職種とも連携しやすいため、医師や看護師といった職種の業務効率向上が期待できるでしょう。
データ損失のリスクが低減できる
WebORCAは、クラウドを利用するため、データサーバーを院内に設置する必要がありません。
クラウド上のデータは、災害に強いデータセンターで安全に保管されています。そのため、機器の故障や万が一の災害時などでも、データの破損や消滅などのリスクを抑えることが可能です。
メンテナンスの負担が低減できる
定期的に必要となる診療報酬改定時対応やバージョンアップなどの作業は、すべてクラウド上でおこなわれます。
そのため、医療機関側で日々のバックアップやプログラム更新作業を実施する必要がありません。作業にともなう更新費用もかからないため、経済的です。
コスト削減できる
一般的なレセコンの場合、メーカー指定のサーバーやパソコンを購入しなければなりません。
一方で、WebORCAを運用する際は、院内のパソコンやタブレットなどが使用できるため、ハードウェアの新調が不要です。
そのため、導入・初期費用などのコスト削減につながります。価格を抑えてシステムを運用したい医療機関におすすめです。
なお、WebORCAのサービス利用料は、基本サービス費用として1医療機関あたり月額2,200円が発生します。(端末台数による変動はなし)
また、セキュリティサービス費用は、初期費用が0円であり、月額550円が発生します。
院内のスペースを削減できる
WebORCAはクラウドを利用するため、院内におけるサーバー設置が不要です。わずらわしい設置作業やケーブル配線なども少ないため、院内スペースを有効活用しやすくなります。
院内でサーバー設置のスペースを確保できない場合におすすめです。
さまざまなクラウドサービスが利用できる
WebORCAでは、以下のクラウドサービスが利用できます。
- 医見書
- 給管帳クラウド版
- 特定健診システムクラウド版
- 地域医療連携のための紹介状作成ツール(MI CAN)
- HPKI電子署名ソフト(SignedPDF Client ORCA)
- DiedAi死亡診断書(死体検案書)作成ソフト
レセプト以外にも、特定健診や介護などに利用できる各種ソフトウェアが使用できます。
WebORCAの利用手順
WebORCAの利用手順は、以下のとおりです。今後導入を検討する場合は、参考にしてください。
- 検討:導入スケジュール、予算、ネットワーク構成等の検討
- お申し込み:日本医師会ORCA管理機構にクラウドサービスのお申し込み
- 接続アカウントの受け取り:WebORCA クラウド版をご利用いただくための接続アカウント(電子証明書等)の受け取り
- 機器導入・設定:端末への電子証明書及びクライアントソフトのインストール、疎通確認
- 日レセ マスタ設定:日レセに医療機関情報等の登録
- 教育・練習:日レセの操作手順の習得、運用
運用開始時は、上記手続き・作業の多くはORCAサポート事業所が代行します。詳しくはお近くの認定サポート事業所にご相談ください。
なお、ご利用までのスケジュールのイメージは、以下のとおりです。
- 1ヶ月目:ご契約後、お申し込み(日レセマスタ設定・データ移行など)
- 2ヶ月目:アカウント受け取り・機器導入設定後、サービス開始。練習実施(クラウドへのアップロード)
- 3ヶ月目:運用開始(本稼働)
上記を経て、レセプト提出の流れになります。
WebORCAの申し込み方法
WebORCAを申し込む場合は、以下の流れに沿って対応する必要があります。
- ORCAMOクラウド サービス利用規約・ORCAMOクラウド セキュリティ利用規約を読む。
- WebORCA クラウド版及びセキュリティサービス利用申込書兼同意書に記入する。
- 支払方法申込書(NTT回線料金への合算)・支払方法申込書(口座振替)・支払方法申込書(請求書払い)のいずれかを印刷・記入し、2.の申込書原本に同封して送る。
現在商用版契約(オンプレミス版利用)中の場合は、商用版の解約も必要です。日医標準レセプトソフト商用版パッケージ利用サービス解約申込書で解約届けを提出しましょう。
WebORCAに関するよくある質問
WebORCAに関するよくある質問は、以下のとおりです。導入・稼働前に疑問点があれば解消しておきましょう。
WebORCAの拡張性は?
WebORCAの拡張性としては、以下の要素が挙げられます。
・電子カルテ
・オーダリング
・レセプトチェック
・PACS
・CRシステム
・予約システム
・お薬手帳用シールラベル
・診察券発行
・自動再来受付
WebORCAはオンライン資格確認に対応している?
WebORCAは、2023年4月から原則義務化された「オンライン資格確認」にも対応しており、追加契約が必要なく利用できます。
医療連携や多職種連携は可能?
組織でのグループ内連携が容易に構築できるため、医療連携や多職種連携は可能です。WebORCAを導入することで、診療効率の向上が期待できます。
まとめ
WebORCAは、日本医師会が提供する日医標準レセプトソフト(日レセ)である「ORCA(オルカ)」のクラウド版ソフトです。
WebORCAは、旧クラウド版と比較すると、動作速度や災害に対する安定性などに優れています。
また、コスト削減や業務効率の向上にもつながるため、おすすめです。拡張性が高く、医療連携や多職種連携などにも対応しているため、今後ますます利便性が高まるシステムといえるでしょう。
新しいクラウド版のシステムの導入を検討している医療機関は、WebORCAの利用をご検討ください。
ORCA連携で導入コスト減!訪問診療向け電子カルテhomis
- AI搭載で書類作成もらくらく
- 月2万円~導入可能
- ORCA連携で導入の手間とコストを大幅削減
>>詳しい内容はこちら
今なら無料でデモ環境をお使いいただけます。お気軽にお申込みください。


